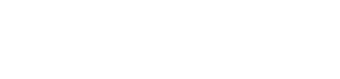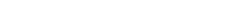1 草原の風 下 宮城谷昌光 中央公論新社
2 12 おすすめ文庫王国 本の雑誌編集部 本の雑誌社
3 小澤征爾さんと、音楽について話をする 小澤征爾/村上春樹 新潮社
4 夢十夜を十夜で 高山 宏 羽鳥書店
5 さいごの色街 飛田 井上理津子 筑摩書房
6 僕のお父さんは東電の社員です 小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味 毎日小学生新聞/森達也 現代書館
7 もし、日本という国がなかったら ロジャー・パルバース著 集英社インターナショナル
8 金魚のひらひら 中野翠 毎日新聞社
9 巴里茫々 北杜夫 新潮社
10 12 このミステリーがすごい! このミステリーがすごい!』編集部 宝島社
3階フェア「デイヴィッド・ヒューム 生誕300年」開催中
只今、当店3階にて、フェア「デイヴィッド・ヒューム生誕300年」を開催中です。
慶應大学出版会から『ヒューム 希望の懐疑主義』を上梓されたばかりの坂本達哉先生(慶應義塾大学教授)にご協力いただき、ヒュームの著書、ヒュームに関する研究書、関連書籍を集めました。
坂本先生からは当フェアにメッセージも寄せていただきました!(↓)
ヒュームといえばカントの「独断の眠り」を覚ました懐疑主義者として有名です。あらゆる政治や宗教、学問の独断がゆるされない現代は、その意味では、ヒュームの時代といってもよいでしょう。同時にヒュームは、「神なき時代」に着実に希望の光を探求した経験主義の思想家でもありました。哲学から社会科学まで、人間本性と文明社会の可能性を最後まで信じたヒュームの思想に学ぶことは少なくないと思います。(坂本達哉)
坂本先生にはヒュームの関連書籍の選書にご協力いただき、慶應大学出版会さんからは「ヒュームと現在」という観点から「脳科学」「行動経済学」の「父」としての側面をクローズアップした選書リストを提供していただきました。また、当店哲学書担当者は、現代のシステム論との関係でヒューム哲学を照射するリストを作成致しました。
ヒュームの哲学を、かつてジル・ドゥルーズは「ポップ哲学」と評していました。
生誕300年を迎え、著書の翻訳もこの数年で飛躍的にタイトル数を増したヒュームを、私たち(ポップ)のものとして読む絶好の機会だと思います。ご高覧いただければ光栄です。
(尚、只今当フェアの栞を作成中です。完成まで少々お待ち下さい)
(3階哲学書担当・三浦)
2月21日追記:当フェアは本日をもちまして終了いたしました。ヒューム関連の本など気になることがございましたら、なんなりとお問い合わせくださいませ。
『おすすめ文庫王国』(本の雑誌社)の文庫ベストテン棚ができました
本の雑誌の増刊『おすすめ文庫王国2012』の中で紹介されている
「本の雑誌が選ぶ2011年度文庫ベストテン」を1階エレベーター前の棚で展開しております。
発売と同時に装丁のかわいい女性と、書店を舞台にしたストーリー展開で読者を魅了した
『ビブリア古書堂の事件手帖』(三上延 メディアワークス文庫)が堂々の1位となり、
深沢七郎の『楢山節考』を彷彿させる、姨捨にあった老婆の生き様を描く
『デンデラ』(佐藤友哉 新潮文庫)や当店で人気のあった『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』(石井好子 河出文庫)など、いろんなジャンルが入り混じったおもしろいランキングが出ております。
是非この機会に実物を手にとってご覧ください。
今週のベストセラー(12月20日調べ)
1 夢 大逆事件を生き抜いた坂本清馬の生涯 鎌田慧 金曜日
2 草原の風 下 宮城谷昌光 中央公論新社
3 みんなで盛り上がる飲み会マジック カズ・カタヤマ 東京堂出版
4 竹中労−左右を越境するアナーキスト 鈴木邦男 河出書房新社
5 さいごの色街 飛田 井上理津子 筑摩書房
6 探訪記者松崎天民 坪内祐三 筑摩書房
7 乱歩彷徨−なぜ読み継がれるのか 紀田順一郎 春風社
8 小澤征爾さんと、音楽について話をする 小澤征爾/村上春樹 新潮社
9 巴里ひとりある記 高峰秀子 新潮社
10 僕のお父さんは東電の社員です 小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味 森達也 現代書館
フリーペーパー『三階』最新号出来ました
哲学・美術書担当者が製作しておりますフリーペーパー『三階』の最新号(第4号)がようやく出来ました。
今号の表紙はジョットの《聖フランチェスコ伝》より《外套の施与》。
今号では、丹生谷貴志氏の新刊『〈真理〉への勇気』(青土社)に収められたテクスト「鏡の魔、或いは砂浜の上の痕跡 en mode sans fin…」と、大友真志氏の写真集『GRACE ISLANDS』(KULA)について、「註」でもあり「メモ」でもあるという意味で「ノート」というかたちで文章を書かせていただきました。丹生谷氏のテクストに関してはミシェル・フーコーの講義『主体の解釈学』でのスピノザへの言及を、大友氏の写真集に関しては、情動と気象、そして「地図作成」という営みについて取り上げさせていただきました。
3階レジカウンター前にて配布しております。ご高覧いただければ幸いです。尚、初刷50部は誤植が多くみっともないのですがご容赦ください。(『三階』製作担当・三浦)