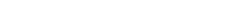上野修さんの新刊『哲学者たちのワンダーランド 様相の十七世紀』(講談社)の特集コーナー、神田神保町店3階哲学・思想書売場にてゆるく始まっています(ポップ、だんだん増えます。フェアの冊子、2月上旬にはできる予定です。のろまで申し訳ないかぎり)。
同書はデカルト、スピノザ、ホッブズ、ライプニッツ、以上4人の17世紀西欧を代表する哲学者を、様相(可能と不可能、偶然と必然といった、事物のあり方)の観点から縦横に、しかもいささかも鹿爪らしくなく論じた快著です。フェアでは同書とともに上野さんの他の著書、上記4人の著作、および哲学への入門書を揃えました。
ジル・ドゥルーズが『スピノザ 実践の哲学』冒頭、エピグラフにバーナード・マラマッドの小説『修理屋』から引用しているのを印象深く記憶している方も多いのではないでしょうか。そこでは登場人物が、スピノザを読んでいるときの精神の昂揚を、「急にまるでつむじ風にでも吹かれたようになって、〔中略〕魔法のほうきに乗っかったような気になります」と語っていたのでした(『修理屋』からの引用は橋本福夫訳)。さて、ここで語られている「つむじ風」とはいったい何でしょう? スピノザの口まねを試みるなら、この「つむじ風」の正体とは、「論証そのものである精神の自動機械の能動性」である、と言うことができるのではないでしょうか。
スピノザは、精神のあり方、感情のタイプを、受動と能動とに分けていました。受動的な感情とは、外的条件に刺激されることで生じる感情のことです。受動感情のひとつ、「憎しみ」のヴァリエーションである「ねたみ」の定義を挙げておきましょう。「ねたみとは人間をして他人の不幸を喜びまた反対に他人の幸福を悲しむようにさせるものと見られるかぎりにおける憎しみそのものにほかならない」(『エチカ』第3部定理24備考。畠中尚志訳)。隷属的な、悲しげな感情ですね。対して能動的な感情、端的に、自らに由来する喜びは、人間精神をして十全な認識へと導く。すなわちこれが、私たちの背中を押す「つむじ風」の正体、という訳です。
ドゥルーズの引用する『修理屋』の登場人物は続けます。「〔スピノザの哲学に〕とくにどういう意味があるかというなら、それはスピノザは自分を自由な人間にしたかったということではないかと思います」。
『哲学者たちのワンダーランド』「序章」で上野さんは、それまで主流であった、「アリストテレス注解」、「プラトン注解」、そしてそれらの「注解の注解」といった哲学のやり方を、17世紀の哲学者たちはやめてしまった、と指摘します。こうした「荒々しいというか、野方図というか、そういうところに彼らの哲学の魅力がある」。『修理屋』において語られていた「自由」は、スピノザに限ったことではなく、『哲学者たちのワンダーランド』が取り上げる17世紀の哲学者たちに共通する魅力であると言えるでしょう。
隷属的に思考することに甘んじず、着の身着のままに、あたかも遊び散らかすがごとくに哲学した、ほとんど「凶暴な」と形容したくなる17世紀の大哲学者たち。彼らの繰り広げる「不思議の国」に飛び込むのに、『哲学者たちのワンダーランド』は、比類のないガイドになります。そして今回企画したフェアでは、なるべく身軽で出掛けた方が、『修理屋』の登場人物の気分で読みはじめることができるだろうと考え、凝った選書は避け、『哲学者たちのワンダーランド』の副読本たる良質な入門書と、デカルト、スピノザ、ホッブズ、ライプニッツの著作でリストを構成してみました。四の五の言わずあっさり飛び込んでしまうのが、17世紀哲学の入門にとって、私はいいと思います。
最後に一言。「波打ち際の砂の表情のように」(ミシェル・フーコー)人間の輪郭が抗しがたく消え去ろうという陽の光の中で考えている、といった手触りを、17世紀哲学に感じます。ルネサンスと近代に挟まれた時代に口を開けた異様な哲学の世界を『哲学者たちのワンダーランド』とともにめぐることは無類の心躍らされる楽しい体験であり、同時に、懐古的遊覧では済まされない不気味なリアリティーで切迫する恐怖(この恐怖もまた、あの「つむじ風」の効果なのです)を伴うことを申し添え、本フェアの案内とさせて頂きます。(神田神保町店人文書担当・三浦)
 (ポスターに使用した図版はデカルトの『哲学原理』第3部から。デカルトは延長空間に真空状態の存在を認めず、空間は物質で充たされている、としました。図は、そうした物質で充たされた宇宙空間にあって、いかにして天体は生成するのかを説明しています。いわゆるデカルトの「渦動説」ですね。)
(ポスターに使用した図版はデカルトの『哲学原理』第3部から。デカルトは延長空間に真空状態の存在を認めず、空間は物質で充たされている、としました。図は、そうした物質で充たされた宇宙空間にあって、いかにして天体は生成するのかを説明しています。いわゆるデカルトの「渦動説」ですね。)